2025年12月号(254号)
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ
山形県東根市
奇抜な逸話のもとへ(その弍)
作家・黒木あるじさんと往く、不思議をめぐる探訪旅。今回は「病」を抱えた先人たちが、平癒を願って祈りをささげた現場を訪ね、その逸話の由来を紐解きます。暮らしと健康に密接にかかわっていた知られざる郷土の物語をお届け。
むかしの人の悩みは、いまとは次元が違う
頭痛や腹痛が起きたとき、あなたはどう対処するだろう。横になってカラダを休め、治らなければ常備薬に頼る。それでも体調が落ち着かなければかかりつけ医を訪ねることもあるだろう。
医者にかかったり薬が当たり前ではない時代
しかし今回「カラダに効く、効いた 逸話のもとへ」というテーマを掲げて取材で訪れた神社や仏閣、堂宇の類は創建が不明なほど古く、仮に鎌倉や安土桃山時代ともなれば手軽に医者へ薬を、というわけにはいかない。カラダの治癒や予防を懇願した先人と、語り継がれている逸話や手法について、その時代に思いを馳せながら学んでみよう。

あるじルポ/酒好き男の幽霊、死後も酒粕を食らい、地蔵として祀られたのちに歯痛を治す
東根市本丸東の四つ辻に建つ素朴な〈かすくらい地蔵〉は、なんとも不可思議な由来を有している。昔、生前酒好きだった男の幽霊が造り酒屋へ毎夕あらわれ、酒粕を食べていくようになった。正体を知った酒屋の主人は四つ辻にこの地蔵を建てて供養してやったが、まもなく主人が虫歯を患い、痛みのあまり地蔵の苔をむしって虫歯にあてると不思議なことに痛みがおさまり、ついには虫歯が治ってしまったのだという。
上記の逸話から〈歯がため地蔵〉とも称されるかすくらい地蔵だが、おなじく歯痛を治すとされる地蔵は京都市伏見区の〈ぬりこべ地蔵〉や岐阜県関ヶ原町の〈六部地蔵〉など全国各地に存在する。その数の多さを見れば、昔の人々にとって歯痛がどれほど悩みの種であったかが容易に理解できる。現在のように歯科医がおらず、そもそも庶民の多くは医者にかかる金などない時代である。致命傷にこそならない反面、耐えがたい痛みで生活の質を著しく下げる虫歯は、人々にとってもっとも身近な病だったのだろう。長きにわたり篤い信仰をあつめていたからこそ、いまも地蔵は素朴な面立ちのままで四つ辻に祀られている……そんな気がしてならない。(黒木あるじ)

地蔵というより板碑。
愛らしい表情が印象的な、かすくらい地蔵
東根市本丸東にある古民家の郷土料理店『梅ヶ枝清水』。その四辻に鎮座するお地蔵様。由来を読み解くと、造り酒屋の主人の行動に呼応するかのように歯痛を鎮めているようにも感じられる。慈悲の心を説く逸話なのかもしれない。
東根市本丸東5-6
場所はこちら(GoogleMap)


作家 黒木あるじ
青森県出身山形県在住。東北芸術工科大学卒業。同大学文芸学科非常勤講師。2010年に「怪談実話 震(ふるえ)」でデビュー。著者に「黒木魔奇録」「怪談四十九夜」各シリーズのほか、ノベライズ作品「小説ノイズ【noise】」や連作短編「春のたましい神祓いの記」などミステリー作品も手がける。河北新報日曜朝刊にて小説「おしら鬼秘譚」を連載執筆中。
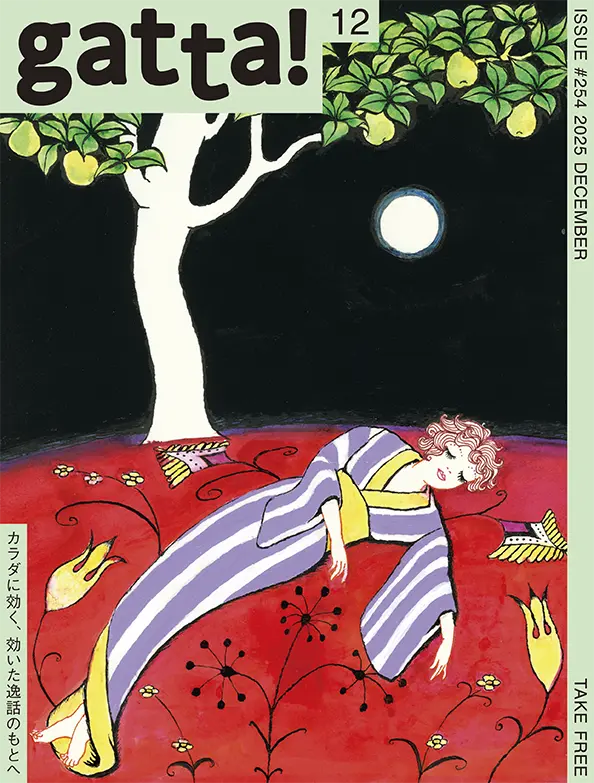
gatta! 2025年12月号
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ
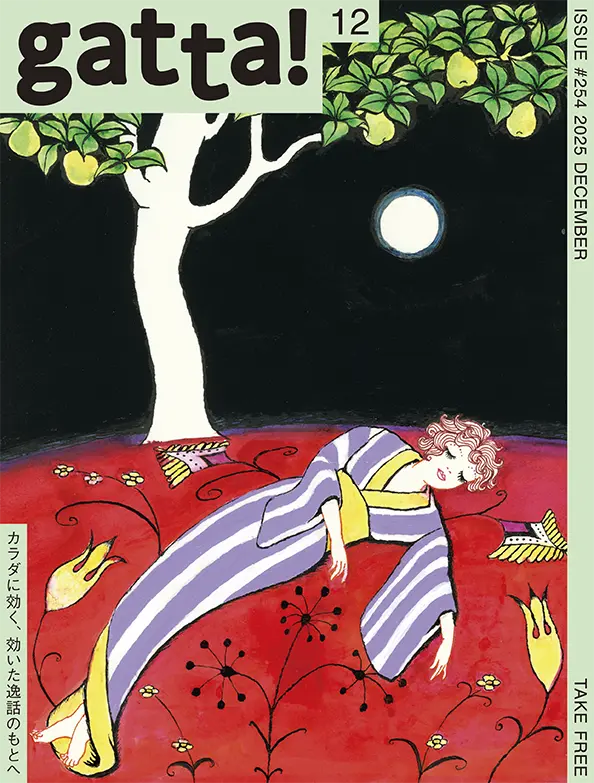
gatta! 2025年12月号
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ














