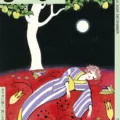2025年12月号(254号)
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ
山形県新庄市、鮭川村、戸沢村、尾花沢市
奇抜な逸話のもとへ(その五)
作家・黒木あるじさんと往く、不思議をめぐる探訪旅。今回は「病」を抱えた先人たちが、平癒を願って祈りをささげた現場を訪ね、その逸話の由来を紐解きます。暮らしと健康に密接にかかわっていた知られざる郷土の物語をお届け。
最上地区で健康祈願の神として崇められる七所明神は、応仁天皇の第二皇子である大山守命にまつわる伝説が由来。王位継承に関し謀反をおこして追われる身となり、北へ向かって逃れてきた大山守命が、新庄の関屋で追討使に捕われて処刑された遺骸が、現在の最上地区の7カ所に奉祀されているという伝説だ。それぞれの明神様を黒木あるじさんとともに巡り、それがいまどのように地域とかかわり崇められているかを見聞した。

歴史ある八向山信仰が残る本合海地区へ
新庄市南西部にある本合海は、最上川の舟運で栄えた歴史を持つ。中世には八向山の南方に八向楯が築城され、その本丸にあたる岩壁中腹には、奥州平泉に向かう源義経も伏し拝んだとされる矢向大明神を祀った矢向神社が建立されている。この地区にも七所明神が祀られており、一帯の土地と五穀の神を守る栄光院によって管理されている。「七所明神(1)」の記事に引き続き、残りの部位を祀る神社の紹介とともに、七所明神守でもある『社稷栄光院』の院主・八向さんからも話を訊くことができた。
豪雨災害を受け社は崩壊御身体はいま
「このあたりは昨年7月の豪雨によって、最上川の支流である新田川が氾濫し、甚大な被害を受けました。その際、本合海の七所神社の社も被害を受け、地盤の緩みから山崩れが起きて倒壊してしまったんです」と八向院主。「不思議なことに御身体は流されず、境内付近に埋まっていたところを土地の人が見つけてくれました」とも。もともと社があった場所には現在、鳥居と一部の部位が残されているが、再建にあたっては移築が検討されているという。
男根 七所明神社(本合海)
子授けと男性特有の病気治癒を願う。2024年夏の豪雨水害と地滑りでお社が消失。本尊は同地区の栄光院で保管されている。
新庄市本合海985
場所はこちら(GoogleMapコード P6JH+HJ 新庄市、山形県)
※MAPコードで検索する際は数字記号と市町村名のどちらもご入力ください。




胴 七所明神社(升形)
安産祈願や胃腸など内臓疾患の治癒を願う。納めてある腹巻を借りて願掛けし、お礼参りに新しい物を奉納する習わしがある。
新庄市升形1713-31
場所はこちら(GoogleMapコード P6XQ+HW 新庄市、山形県)


右足 七所明神社(戸沢村下松坂)
内陣には、右足の悪い人が願掛けに奉納したと思われる義足や靴、靴下、スリッパなどが納められている。
戸沢村大字松坂東塩沢632-3(諏訪神社内)
場所はこちら(GoogleMapコード Q58V+6X 戸沢村、山形県)



左足 七所明神社(鮭川村京塚)
京塚愛宕神社と一緒に合祀されており、社の周辺には稲荷の小社、弁才天、湯殿山の大石碑がある。また、東方の峰には山神社があり、御神体の男根形の大木棒は毎年4月3日(旧3月3日)に地元の子ども達が「山の神勧進」の奇祭を行う。さらに、境内には農村歌舞伎の土舞台跡があり、以前は村芝居(県無形民俗文化財・鮭川歌舞伎)がここで上演され賑わいをみせた。
最上郡鮭川村京塚1118(京塚愛宕神社内)
場所はこちら(GoogleMapコード R68Q+HG 鮭川村、山形県)


腰 伊豆七所両神社(尾花沢市名木沢)
大山守命の願いとは裏腹に七太刀浴びせられ誤って8つに切り分けてしまったため、残りのひとつ(腰)をここ名木沢に葬り、祀った「もう一つの七所明神」とも呼ばれている。諸説あるが遺骸を投げた沢であったことから投げ沢と呼ばれていたのが名木沢になったなど、様々な伝承が残る地である。
尾花沢市名木沢西裏747
場所はこちら(GoogleMapコード M85X+P2 尾花沢市、山形県)

本合海地域で24代続く社稷『栄光院』
最上地域を中心に行われている師走の伝統行事「さんげさんげ」。ここ栄光院でも毎年年末になると、不動明王など地元各社の138体にもおよぶ御神体に祈る厄落としを兼ねて執り行われている。『白蛇大権現』もその社のひとつであり、管理者である栄光院の八向宮司は「昨年末の催事では地域住民の健康と幸せを願った」と話す。
「令和6年夏の大雨でこの辺り一帯は大変な惨事に見舞われた。近くにあった本合海七所明神は大雨被害にあってしまったが、白蛇大権現の社は免れた。白蛇大権現様のお社は昔から最上川の乗船場を見守り続けてきた存在で、地域の人々がいまも大切に守り継いでいる」と続ける。

八向山、八向楯、矢向神社を代々守る由緒ある社として
本合海の『七所明神』はもとより、最上川右岸の八向山山頂に天正年間(1573年から92年)に木戸周防が築いたとされる城(楯)の『八向楯』、そして古来より最上川を上下する舟人の信仰が篤く、文治3年(1187年)に兄頼朝と対立した源義経はが舟で最上川をさかのぼり、本合海で上陸して奥州平泉に向かうが、その時に義経も矢向大明神を伏し拝んだと「義経記」に記されている『矢向神社』。また、健康祈願の神として、吹き出物・歯痛を治すとして崇められる『白蛇大権現』など地元の様々な社や史跡の管理を務める『栄光院』。かつて兄頼朝に追われた義経一行が平泉に逃げのびる途中に、栄光院があるこの場所で一行が宿泊をした記録が残っているという。





八百万の神々と向き合い守り継ぐ存在
この『栄光院』では、土地の神と五穀の神、国家を意味する「社稷(しゃしょく)」を冠し、はるか昔から当地の八百万の神々に捧げる祭祀を主宰してきた。たとえば先に紹介した「さんげさんげ」は、出羽三山や村内の神仏を呼び出して礼拝し、翌年の豊作や健康を祈願する。こうした神事はかつて日本のあちこちで執り行われていたものの、我々の暮らしや社会の変化によって年々縮小し、またそれらを執り行う宮司や験者の減少も相まって、希少な存在になりつつある。

手を合わせ祈る日本の原風景がここに
「じつは私も八向家の次男坊。長男は進学で首都圏で暮らし、地元に残った私が跡を継ぎました。25代についてはいまのところ私の娘が継ぐと申し出てくれていますが」と八向宮司。「私ひとりで100以上あるお社の管理をするのは難しく、多くはその地域のかたがたにお任せしています」とも。神々に手を合わせ祈りを捧げることが、天候を左右したり病を治すための策でないかもしれない。だがそうあってほしいと信じ、心に拠りどころを持つことで前を向くことができたらそれで充分だ。人々の信心によって幾多の時間が紡がれてきたその歴史は尊い。


作家 黒木あるじ(記事監修)
青森県出身山形県在住。東北芸術工科大学卒業。同大学文芸学科非常勤講師。2010年に「怪談実話 震(ふるえ)」でデビュー。著者に「黒木魔奇録」「怪談四十九夜」各シリーズのほか、ノベライズ作品「小説ノイズ【noise】」や連作短編「春のたましい神祓いの記」などミステリー作品も手がける。河北新報日曜朝刊にて小説「おしら鬼秘譚」を連載執筆中。
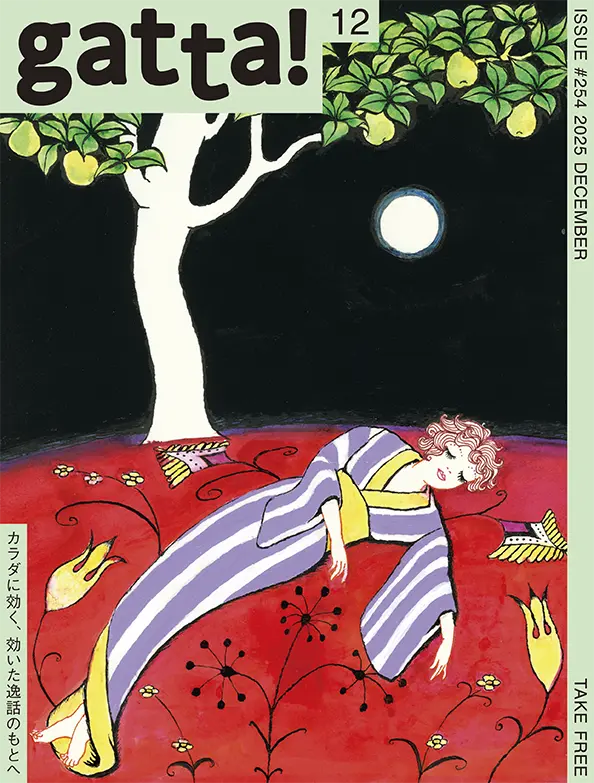
gatta! 2025年12月号
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ
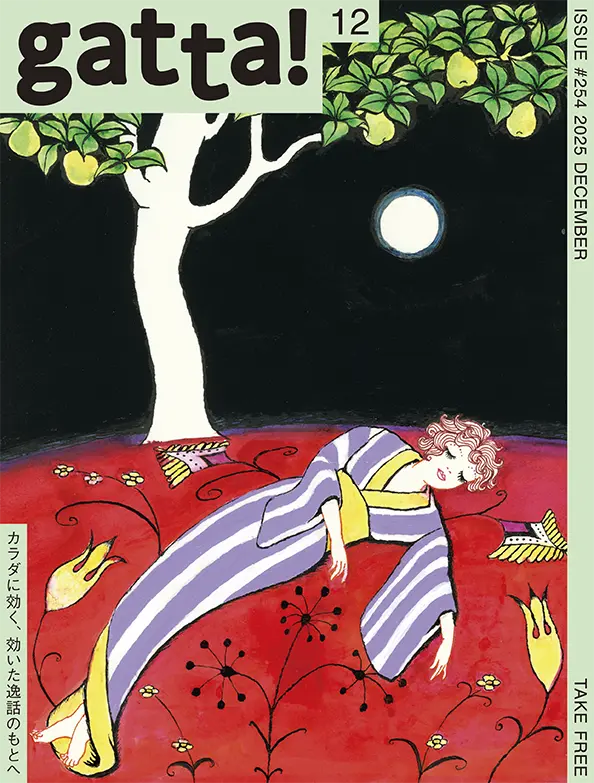
gatta! 2025年12月号
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ