2025年12月号(254号)
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ
山形県山形市滑川
奇抜な逸話のもとへ(その参)
作家・黒木あるじさんと往く、不思議をめぐる探訪旅。今回は「病」を抱えた先人たちが、平癒を願って祈りをささげた現場を訪ね、その逸話の由来を紐解きます。暮らしと健康に密接にかかわっていた知られざる郷土の物語をお届け。
むかしの人の悩みは、いまとは次元が違う
頭痛や腹痛が起きたとき、あなたはどう対処するだろう。横になってカラダを休め、治らなければ常備薬に頼る。それでも体調が落ち着かなければかかりつけ医を訪ねることもあるだろう。
医者にかかったり薬が当たり前ではない時代
しかし今回「カラダに効く、効いた 逸話のもとへ」というテーマを掲げて取材で訪れた神社や仏閣、堂宇の類は創建が不明なほど古く、仮に鎌倉や安土桃山時代ともなれば手軽に医者へ薬を、というわけにはいかない。カラダの治癒や予防を懇願した先人と、語り継がれている逸話や手法について、その時代に思いを馳せながら学んでみよう。

耳だれに悩む人が日参してお参りしていた地蔵様
御堂には大小12体の石地蔵が祀られ、3〜6センチの平らな丸石に穴の空いた石が供えられている。「耳だれ地蔵」の板看板がある通り、中耳炎や外耳道炎などの細菌感染等で膿の出る症状に悩む人から信仰されたもの。また、石に開いた穴が目がよく見えることの象徴とされ、「目の通りが良くなるように」という願いを込めて眼病平癒を祈願して奉納されたという謂れもある。かつてはお堂の背後を流れる滑川向かいの山の中腹、大きな岩の上に安座していたというが、いまは国道の陰に隠れながらひっそりと道ゆく人々を見守り続けている。

国道に沿った小道にある、
道祖神とならぶ滑川愛宕地蔵
山形市滑川地区、山形県と宮城県の峠道となる笹谷へ向かう国道286号沿にある『禅昌寺』と滑川の間を通る小道にお堂が建ち、滑川愛宕地蔵とともに祀られている。この地区出身の50代女性は「小さい頃、お地蔵様にお供えを持っていくっていう夏の肝試しをやった」と教えてくれた。また、小道を挟んですぐ向かいにある滑川禅昌寺境内には、最上流算学師会田算左衛門安明の石碑が立っている。安明は、当時隆盛をきわめた算学関流の封建性に飽きたらず、新たに独自の着想によって最上流という数学を考え出した人物。
山形市滑川260(国道286号近く)
場所はこちら(GoogleMap)


作家 黒木あるじ(記事監修)
青森県出身山形県在住。東北芸術工科大学卒業。同大学文芸学科非常勤講師。2010年に「怪談実話 震(ふるえ)」でデビュー。著者に「黒木魔奇録」「怪談四十九夜」各シリーズのほか、ノベライズ作品「小説ノイズ【noise】」や連作短編「春のたましい神祓いの記」などミステリー作品も手がける。河北新報日曜朝刊にて小説「おしら鬼秘譚」を連載執筆中。
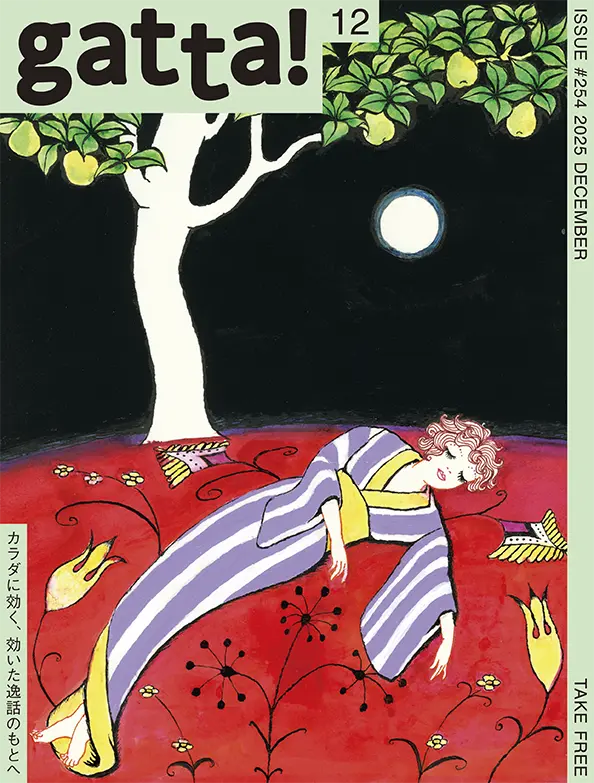
gatta! 2025年12月号
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ
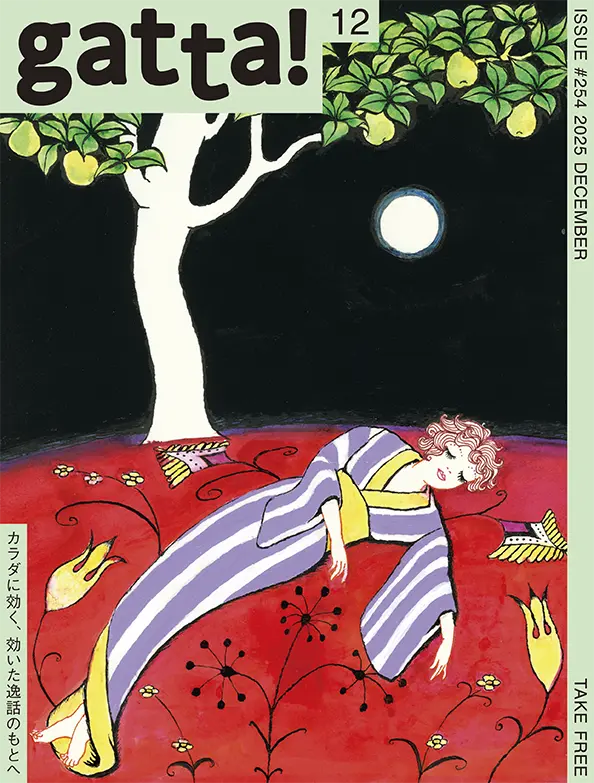
gatta! 2025年12月号
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ














