2025年12月号(254号)
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ
山形県東根市
奇抜な逸話のもとへ(その壱)
作家・黒木あるじさんと往く、不思議をめぐる探訪旅。今回は「病」を抱えた先人たちが、平癒を願って祈りをささげた現場を訪ね、その逸話の由来を紐解きます。暮らしと健康に密接にかかわっていた知られざる郷土の物語をお届け。
むかしの人の悩みは、いまとは次元が違う
頭痛や腹痛が起きたとき、あなたはどう対処するだろう。横になってカラダを休め、治らなければ常備薬に頼る。それでも体調が落ち着かなければかかりつけ医を訪ねることもあるだろう。
医者にかかったり薬が当たり前ではない時代
しかし今回「カラダに効く、効いた 逸話のもとへ」というテーマを掲げて取材で訪れた神社や仏閣、堂宇の類は創建が不明なほど古く、仮に鎌倉や安土桃山時代ともなれば手軽に医者へ薬を、というわけにはいかない。カラダの治癒や予防を懇願した先人と、語り継がれている逸話や手法について、その時代に思いを馳せながら学んでみよう。

あるじルポ/百日咳を防いで地域より篤い信仰を集める、おごそかな佇まいの地蔵菩薩
東根市の県道沿いに建つ、赤い屋根の拝殿が特徴的な荷渡地蔵尊。舟運の荷渡しが名前の由来だというこの地蔵は、呼吸器感染症の「百日咳」にご利益があるとされている。現在でこそワクチンが普及している百日咳だが、ワクチン普及以前は有効な治療法のない疾患で、とりわけ乳幼児は重篤化する傾向にあったのだとか。もしかすると荷渡地蔵の百日咳予防は、我が子を思う親の気持ちが生みだした信仰なのかもしれない。
それにしても、なぜ舟運を守る地蔵が百日咳を防ぐのか。一説によれば咳き込む声が鶏の鳴き声に似ていることから「鶏=にわたり」の語呂合わせで生まれた信仰らしい。なんとも不可解な理由だが、そもそも荷渡地蔵は謎が多い。山形市双月の荷渡権現や白鷹町下山の庭渡神社ほか、近似した神社が県内外に存在するのだ。名称は二渡・鬼渡・仁和多利など複数で読みも多岐にわたる。斯様にミステリアスな神仏とあっては、感染症を防ぐ霊験も妙に肯けるというものではないか(黒木あるじ)





東根と楯岡の境にあり荷の受け渡し場所でもあった
荷渡地蔵尊(にわたしじぞうそん)
東根市内から村山市方面へ向かい、堂ノ前公園を1.5kmほど走ると右手に現れる。地蔵尊の由来によれば、かつてこの辺りの圃場一体は『藻が湖(もがうみ)』という広大な湖だったという伝説が残り、湖のほとりとなる東の山岸を東根、西の山岸を西根(寒河江市)と呼ばれ、舟で行き来していたという。この「モガウミ」という呼称が「最上」の地名になったとされる。
東根市東根甲(県道304号沿)
場所はこちら(GoogleMap)


作家 黒木あるじ
青森県出身山形県在住。東北芸術工科大学卒業。同大学文芸学科非常勤講師。2010年に「怪談実話 震(ふるえ)」でデビュー。著者に「黒木魔奇録」「怪談四十九夜」各シリーズのほか、ノベライズ作品「小説ノイズ【noise】」や連作短編「春のたましい神祓いの記」などミステリー作品も手がける。河北新報日曜朝刊にて小説「おしら鬼秘譚」を連載執筆中。
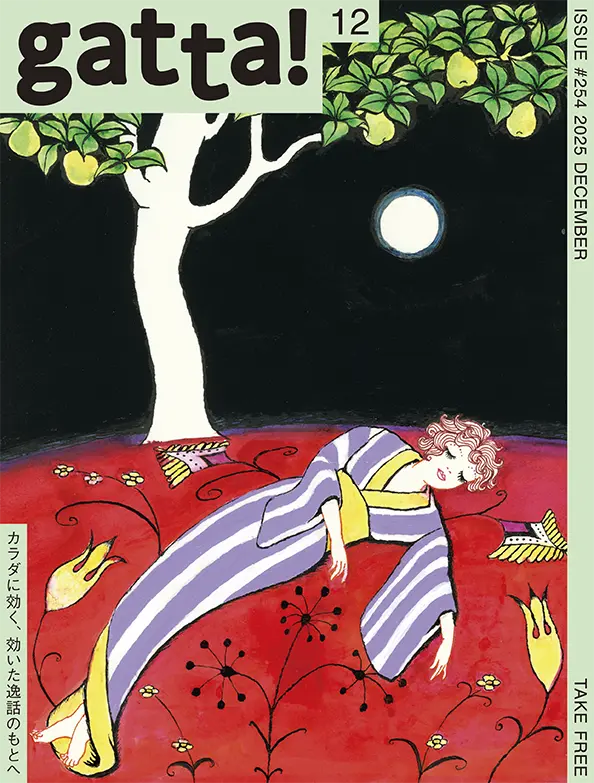
gatta! 2025年12月号
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ
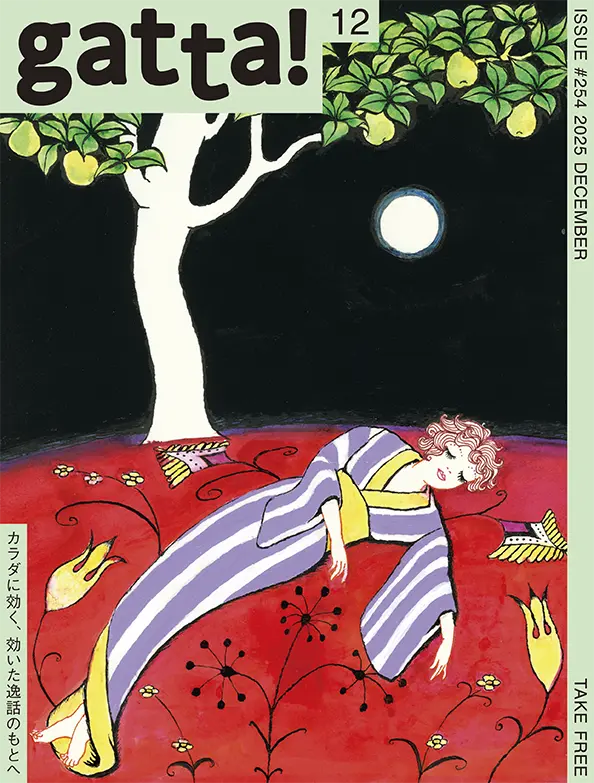
gatta! 2025年12月号
特集|カラダに効く、効いた 逸話のもとへ














