New Article
-
特集|最上地方

訪問先でかけられる言葉やもてなしに、真室川の人の温かさを実感。
-
特集|最上地方

ローカル駅おさんぽ旅(真室川駅編、赤湯駅編)
-
Magazine
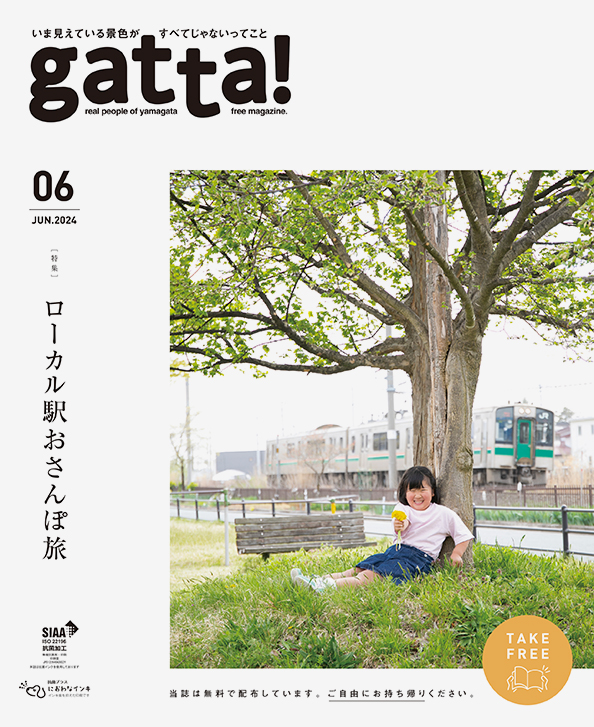
gatta! 2024年6月号 ローカル駅おさんぽ旅
-
チマタの話題

つながりを彩る、山形発信のアートと食のフェスティバル『IRODORI』
-
特集|庄内地方

品質本位の姿勢は変わらず。遊佐から世界へ、上質なウイスキーを
-
特集|村山地方

時代によってお酒の好みは変遷しているらしいが。では山形は?
Magazine
gatta! 2024年6月号 vol.236
ローカル駅おさんぽ旅
昨年秋にお届けした路線旅特集が好評だったので、お出かけシーズンまっ只中に第2弾を決行。今回は電車だから叶う“ほろ酔い”情報など街あるきならではの楽しみかたを中心に掲載。
Popular
News
Advertising
広告掲載のご案内
お客様の持ち味や本質を「正しく伝える」ための、取材と編纂を軸とした広告制作。また、ウエブ記事掲載やソーシャルネットワーキングサービス配信、動画制作・配信などを、誌面広告とともに連動するコンテンツ制作も手がけております。


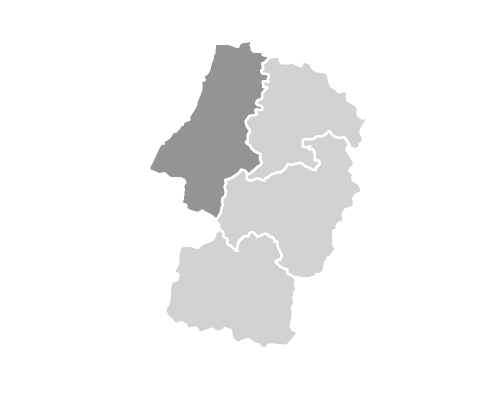 庄内地方
庄内地方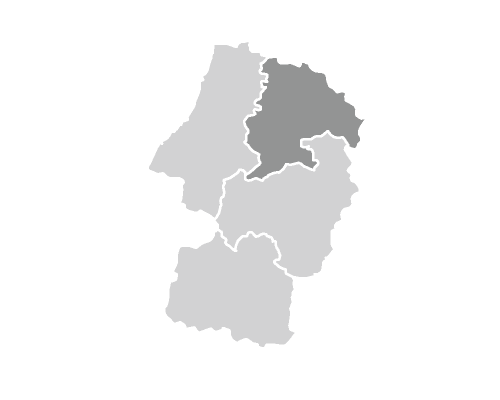 最上地方
最上地方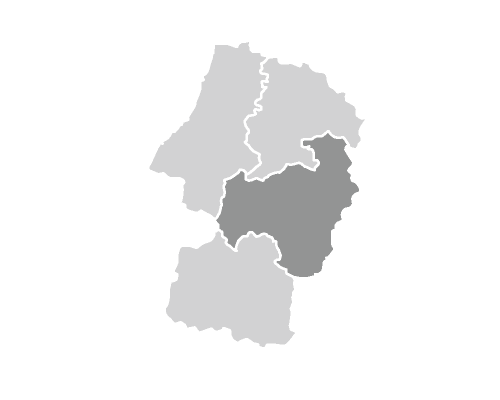 村山地方
村山地方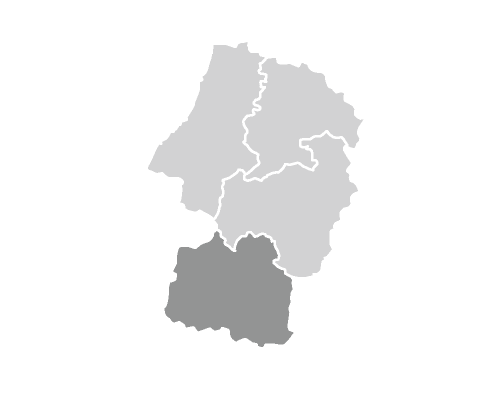 置賜地方
置賜地方